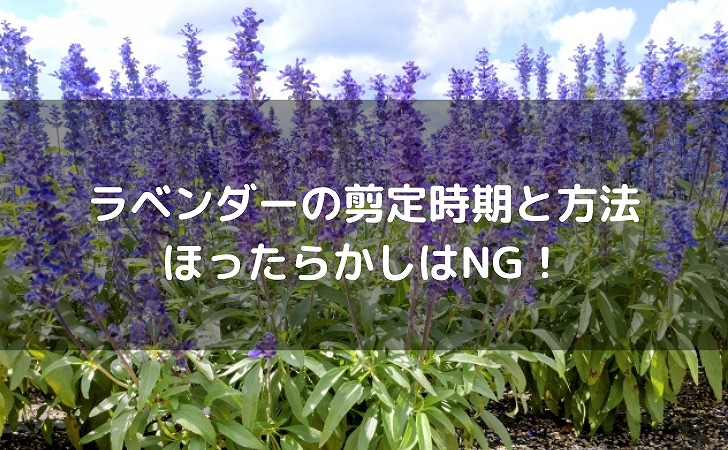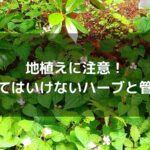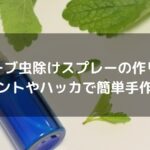ラベンダーは爽やかな香りと美しい紫色の花が咲く人気のハーブですが、適切なケアを怠ると、美しさを長く維持することができません。
多くの方が「丈夫で育てやすい」というイメージを持つラベンダーですが、実は適切な剪定をしないと健全に育たない植物なのです。
放置すると木質化が進み、風通しが悪くなり、蒸れによる枯死の原因となります。
本記事では、ラベンダーに適切な管理が必要な理由から、正しい剪定の時期や方法まで、健康に育てるための重要なポイントを詳しく解説します。
ラベンダーをほったらかしで育てるのはNGな理由
ラベンダーをほったらかしで育てるのは良くない理由としては次の2点が挙げられます。
- 木質化してしまうから
- 蒸れて枯れる原因になるから
それぞれの理由について、もう少し詳しくお伝えしていきます。
木質化してしまうから
ラベンダーをほったらかしにしてしまうと、木質化して枯れてしまう可能性があります。木質化とは、茎が木のように硬くなり、柔軟性や水分が失われる現象のことです。
木質化してしまうと、以下の問題が発生します。
- 開花量が減る: 茎が硬くなることで、水分や養分が花芽にうまく行き渡らず開花量が減る
- 蒸れやすくなる: 病気や害虫が発生しやすくなってしまう
- 枯れやすくなる: 茎が水分を吸収しにくくなり、枯れやすくなってしまう
ラベンダーを木質化させないためには、定期的に剪定を行うことが大切です。
蒸れて枯れる原因になるから
ラベンダーは乾燥した環境を好み、蒸れを嫌う植物です。
そのため、適切な剪定を行わないと蒸れて枯れてしまう原因になります。特に梅雨時期や夏場などは、空気中の湿度が高くなるため、剪定で風通しを良くすることが重要です。
剪定は、ラベンダーが伸びすぎた枝を切り戻すことで、風通しを良くし蒸れを防ぐ効果があります。
また、剪定することで、新しい枝が伸び花付きも良くなります。
ラベンダーの剪定の種類と方法
ラベンダーを健康に育てるためには、剪定が欠かせませんが、剪定には大きく分けて弱剪定と強剪定の2種類があります。
弱剪定は、花が終わった後の初夏から夏にかけて行い、強剪定は、冬の終わりから早春(2~3月頃)に行います。
剪定をしないと、ラベンダーは枝が伸びすぎて、花付きが悪くなったり株が弱って枯れてしまうこともあります。また、病気や害虫が発生しやすくなるため、定期的に剪定を行うことが大切です。
ラベンダーの剪定は、適切な時期と方法で行うことで、株を健康に保ち美しい花を楽しむことができます。
弱剪定
弱剪定とは、花後の花茎を切り戻す方法です。これにより、風通しが良くなり蒸れを防ぎ、新しい芽の成長を促して株を若返らせる効果があります。
【方法】
- 花が咲き終わった花茎の下に葉を2~3対残して切り戻します
- 切り口は斜めにカットすると雨水が溜まりにくく、病気予防になります
- 株全体の形を整える程度の軽い剪定です
【適切な時期】
- 花が咲き終わってから1ヶ月以内(初夏~夏)
- 地域によって異なりますが、主に6月下旬~8月頃
【注意点】
- 鋭利なはさみを使用し、枝を傷つけないよう丁寧に切りましょう
- 新芽を切らないように注意してください
- すべての花茎を切り戻すことで、風通しがよくなります
- 花後なるべく早く行うことで、余分なエネルギーを使わず、翌年の開花に備えられます
強剪定
強剪定は弱剪定よりも深く切り込む剪定方法で、過度の木質化を抑制し株を若返らせる効果があります。
【方法】
- 地上部から10~15cm程度を残して、大胆に切り戻します
- 株全体の形を考えながら、古い木質化した部分を中心に剪定します
- 切り口は斜めにカットします
【適切な時期】
- 冬の終わりから早春(2~3月頃)
- 厳寒期を避け、気温が上昇し始める時期が適しています
【注意点】
- 強剪定は株にストレスを与えるため、毎年行うのではなく2~3年に一度行います
- 切りすぎると枯れる可能性があるので、緑の葉が残る部分まで切り戻します
- 芽吹きの兆しが見える場合は、その部分を残すように注意します
- 一度にすべての枝を強剪定せず、株の状態に応じて剪定量を調整しましょう
- 樹齢が進んだラベンダーほど、強剪定に耐えられない場合があります
強剪定は過度の木質化を抑制し株を若返らせる効果がありますが、リスクも伴います。ラベンダーの種類や年齢によっても剪定の方法を調整すると良いでしょう。
イングリッシュラベンダーは比較的強剪定に耐性がありますが、フレンチラベンダーなどは注意が必要です。
定期的な弱剪定と必要に応じた強剪定を組み合わせることで、ラベンダーを長く健康に育てることができます。
ラベンダーの剪定のコツ
ラベンダーの剪定のコツとして、以下のポイントをご紹介します。
- 新芽を切らない方法
- 開花後のラベンダの処理
- 剪定しすぎにならないためのコツ
- 剪定後の水やりのポイント
それぞれのポイントについて詳しくお伝えしていきます。
新芽を切らない方法
ラベンダーの剪定では、新芽を切らないことが大切です。新芽は来年以降の花付きに大きく影響するからです。
新芽を切ってしまうと、花数が減ったり、花が咲かなくなったりする可能性があります。
そこで、ラベンダーの剪定では、「弱剪定」と「強剪定」を使い分けることが大切です。
強剪定を行う際は、緑の葉が残る部分まで切り戻し新芽の兆しが見える場合はその部分を残すよう注意しましょう。
開花後のラベンダーの処理
ラベンダーは放っておくと木質化して蒸れて枯れてしまうため、剪定が必要です。
剪定の種類は弱剪定と強剪定の2つがあり、それぞれ目的が異なります。
剪定時期は弱剪定が花後すぐ(主に6月下旬~8月頃)、強剪定が冬の終わりから早春(2~3月頃)に行います。剪定する際は、新芽を切らないように注意し、剪定しすぎないようにしましょう。
剪定しすぎにならないためのコツ
剪定しすぎを防ぐためには、以下のポイントに注意しましょう。
- 弱剪定では花茎の下に葉を2~3対残して切り戻す
- 強剪定では緑の葉が残る部分まで切り戻す
- 強剪定は株にストレスを与えるため、毎年行うのではなく2~3年に一度行う
- 樹齢が進んだラベンダーほど、強剪定に耐えられない場合があるので注意する
- 一度にすべての枝を強剪定せず、株の状態に応じて剪定量を調整する
剪定後の水やりのポイント
ラベンダーの剪定後の水やりは、剪定の種類によって異なります。
弱剪定後は通常通りの水やりを続けますが、強剪定後は株の回復を促すため、土の表面が乾いたらたっぷりと水やりをするようにしましょう。ただし、与えすぎは禁物です。
水を与えすぎると、根腐れを起こしてしまう可能性があるからです。
基本的にラベンダーは乾燥気味を好むため、水やりの量は、土が湿る程度で十分です。また、水やりは、朝に行うのがベストです。
葉や茎が濡れたまま夜を迎えると、病気の原因になることがあります。
適切な水やりと剪定を行うことで、ラベンダーは長く健康に育ちます。剪定の時期や方法を理解して、美しい花を咲かせましょう。
まとめ:ラベンダーはほったらかしではいけない理由
ラベンダーは適切な剪定を行わないと、木質化して枯れる原因となり、蒸れによる病気の発生リスクも高まります。放置すると開花量が減少し、健全に育たなくなります。
ラベンダーの剪定には「弱剪定」と「強剪定」の2種類があります。弱剪定は開花後の初夏から夏に行い、花茎の下に葉を2~3対残して切り戻します。
一方、強剪定は冬の終わりから早春に行い、株元から10~15cm程度を残して大胆に切り戻します。強剪定は2~3年に一度が適切です。
剪定の際は新芽を切らないよう注意し、切り口は斜めにカットして雨水が溜まらないようにしましょう。
また、剪定後の水やりも重要で、特に強剪定後は株の回復を促すため、土が乾いたらたっぷりと水を与えてください。ただし、ラベンダーは基本的に乾燥気味を好むため、水のやりすぎには注意が必要です。
適切な剪定と水やりの管理を徹底すれば、ラベンダーは長く健康に育ち、毎年美しい花を咲かせ続けるでしょう。