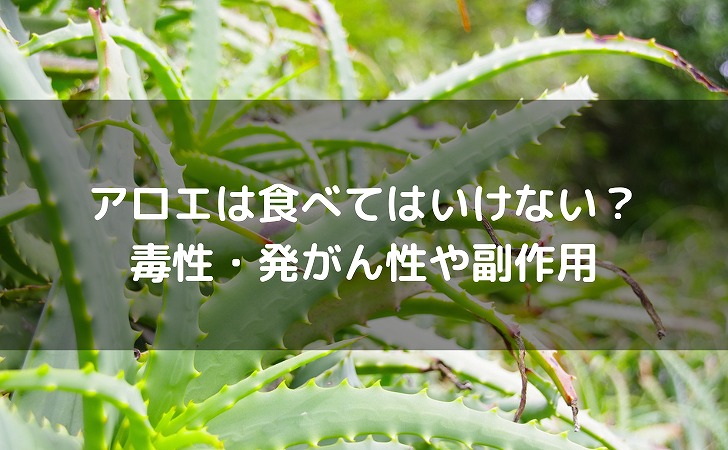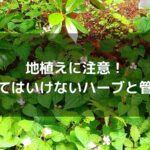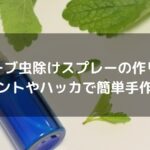アロエは古くから薬用植物として重宝されてきましたが、食べてはいけないと言われることもあります。
主な原因はアロエに含まれる毒性が理由ですが、正しい知識を持つことでアロエが持つ効果や効能を安全に得ることができるはずです。
本記事では、アロエの毒性・発がん性や副作用について詳しく解説するとともに、食用アロエと観賞用アロエの違い、アロエを食べる際の注意点、そしてアロエベラ・キダチアロエに期待できる健康効果についてもご紹介します。
アロエに関する疑問を解決し、安全かつ効果的にアロエを生活に取り入れるための参考にしてみてください。
アロエを食べてはいけないと言われる理由
アロエは健康に良いとされる植物ですが、食べてはいけないと言われる理由には次の3つが挙げられます。
- 食用と観賞用がある
- 毒性が含まれる
- 発がん性物質が含まれる可能性がある
アロエには500種類以上が存在し、そのうち食用とされるのはアロエベラ(Aloe vera))、キダチアロエ(Aloe arborescens)のみです。
観賞用のアロエを摂取すると腹痛や下痢などの症状を引き起こす可能性があります。
食用アロエは葉の内部のゲル状の部分のみが食用となり、皮や黄色い樹液には刺激性成分が含まれています。
適量であれば安全に摂取できますが、過剰摂取は下痢や腹痛、電解質のバランス異常などの副作用を引き起こす可能性があります。また、妊娠中や授乳中、特定の疾患がある場合は、摂取を避けるべきです。
アロエは食用と観賞用の種類があること、食用であっても皮や黄色い樹液には毒性が含まれている点が食べてはいけないと言われる主な理由。
アロエの葉に含まれる毒性・発がん性物質
アロエは様々な効能が期待できることから幅広く活用される一方で、毒性を持つ部分もあり注意が必要です。
アロエには、主に以下の2種類の毒性成分が含まれています。
- アロイン
- アントラキノン
アロイン
アロインは、アロエの葉の表皮のすぐ下に含まれる成分です。腸のぜん動運動を活発にして便秘を改善する作用があります。
ただし、大量に摂取すると以下のような副作用が出る可能性があるとされています。
- 腹痛
- 下痢
- 吐き気
- 嘔吐
なお、発がん性の可能性については、「発がん性の作用あり」と「発がん性に関する報告はない」といった研究結果があり、現時点では正確に判断することは困難です。
アントラキノン
アントラキノンは、アロエの葉の表面近くに含まれる成分です。アロインと同じく、腸の蠕動運動を活発にして便秘を改善する作用があります。
アントラキノンはアロイン同様、発がん性については肯定・否定両方の研究結果があり、正確にはわかっていないのが実情です。
また、大腸メラノーシスという現象を引き起こす可能性があります。
大腸メラノーシスとは、アロエやセンナなどのアントラキノン系物質を長期服用、乱用することで大腸壁が黒くなる現象です。
アロエは適量を摂取すれば健康に良い効果が期待できますが、大量に摂取すると危険なため注意が必要です。特に、妊婦や授乳中の方、小児、お年寄りは、摂取量に十分注意してください。
主な副作用は次のとおりです。
- 腹痛
- 下痢
- 吐き気
- 嘔吐
- 大腸メラノーシス
以上のことから、アロエを摂取する際には、以下の点に注意してください。
- 1日あたりの摂取量は、100g程度にする。
- 葉の表面近くの部分は、毒性成分が多いので避ける。
- 妊婦や授乳中の方、小児、お年寄りは、摂取量に十分注意する。
- 副作用が起きた場合は、すぐに医師の診察を受ける
食用アロエの健康効果
アロエベラ
主な効果
| 消化器系サポート | 腸の蠕動運動を促進し、便秘改善に効果的 |
| 栄養素 | ビタミン、ミネラル、アミノ酸を含み、栄養補給に役立つ |
| 血糖値管理 | 一部の研究では血糖値の調整をサポートする可能性が示されている |
| 免疫機能向上 | 多糖類が免疫機能を調整する効果があるとされている |
| 抗炎症作用 | 体内の炎症を抑制する作用がある |
食べ方の特徴
最も一般的に食用とされ、無味または微かな苦味があり、料理やドリンクに加えやすいです。
キダチアロエ
主な効果
| 解毒作用 | 体内の毒素排出を促す効果があるとされている |
| 抗酸化作用 | アロエベラよりも強い抗酸化作用があるという研究もある |
| 免疫強化 | 免疫システムを活性化する作用が強いとされている |
| 整腸作用 | 便秘改善効果がありますが、アロエベラよりも作用が強い傾向がある |
食べ方の特徴
アロエベラよりも苦味が強く、蜂蜜などと混ぜて食べることが多いです。日本では「アロエ健康法」で知られています。
食べにくいため、サプリでの摂取や生絞りジュースで飲むのが一般的です。
整腸作用を期待して摂取する人が多いですが、同時に抗酸化作用なども得られるため特に女性の人気が高いのが特徴です。
アロエを食べる際の注意点
アロエを食べる際には、食用アロエであるアロエベラ・キダチアロエ以外のものを食べないように注意が必要です。
また、皮を剥いて中のゼリー状の部分だけを食べましょう。皮の部分には毒性があるので、食用アロエであっても食べられる部位はしっかりと知っておく必要があります。
アロエは適量であれば健康に良い効果をもたらしますが、妊娠中や授乳中の方は摂取を避けた方が良いでしょう。
アロエベラとキダチアロエの見分け方
アロエベラとキダチアロエの見分け方について、主な特徴を一覧表にまとめました。
| 特徴 | アロエベラ | キダチアロエ |
| 葉の形状 | 厚みがあり、幅広で平たい | 細長く、断面が三角形に近い |
| 植物の高さ | 低く成長、地面に近い | 高く成長し、木立ちになる |
| 葉の色 | 緑色(時に白い斑点あり) | 青みがかった緑色 |
| 葉の縁 | 小さな白い歯状の突起 | 大きく鋭い赤褐色の棘 |
| 成長パターン | ロゼット状 | 幹を形成し、木のように成長 |
アロエの効果や副作用に関するQ&A
ここでは、アロエの効果や副作用に関するQ&A(質問&回答)を紹介します。
- やけどにアロエは効果があるって本当?
- アロエは生で食べられる?
- アロエは肌荒れにも効果がある?
上記の問いについて詳しく回答していますので、参考にしてみてくださいね。
やけどにアロエは効果があるって本当?
アロエは、やけどの治療に効果があるとされる伝統的な自然療法です。
アロエベラの葉に含まれるアロエベラゲルは、抗炎症作用や鎮痛作用があることが知られており、やけどの痛みや炎症を軽減する効果が期待でき、市販の軟膏に含まれていることもあります。
しかし、アロエの効果については科学的根拠が十分とは言えません。やけどの程度によっては、アロエ軟膏を塗るよりも効果的な治療法が存在するため、やけどを負った場合は、まず冷やすなどの応急処置を行い、その後医師の診察を受けることが重要です。
また、アロエベラゲルは、まれにアレルギー反応を引き起こす可能性があります。アロエを使用する前に、少量を肌に塗ってパッチテストを行い、異常がなければ使用してください。
なお、アロエベラゲルは、初期段階である軽度のやけどにのみ効果があるとされています。重度のやけどには使用しないでください。
アロエは生で食べられる?
食用として用いられるアロエベラなどの食用種であれば、適切な処理をすれば生で食べることができますが、独特の苦味があるためそのまま食べるのは難しいでしょう。
適切な処理とは、葉の外皮と黄色い樹液(ラテックス)を完全に取り除き、透明なゲル部分だけを使用することです。この樹液には下剤成分が含まれているため、必ず除去する必要があります。
スムージーやヨーグルトに混ぜたり、蜂蜜をかけて食べるなど、アレンジして食べるのが一般的です。
また、生のアロエは少量から試すようにし、お腹の調子に異変を感じた場合は摂取を中止しましょう。
アロエは肌荒れにも効果がある?
アロエは肌荒れにも効果があるとされています。
アロエには、肌荒れの原因となる炎症を抑える、抗菌作用や保湿作用など、肌の健康に役立つさまざまな成分が含まれています。
アロエに含まれる主な成分とその効果は以下の通りです。
- アロエシン(Aloesin): 抗炎症作用、抗菌作用、保湿作用
- アロエマンナン: 保湿作用
- アロイン: 皮膚のターンオーバーを促進
- ビタミンC、E: 抗酸化作用
これらの成分が、湿疹やかゆみ、あせも、かぶれ、ニキビなどの肌荒れ対策に効果が期待できるとされています。
実際に、ハンドクリームや軟膏など、アロエが含まれている製品が数多く市販されています。
まとめ:アロエは食べてはいけないと言われる理由と健康効果
アロエには食用と観賞用の種類があり、食用は主にアロエベラとキダチアロエのみです。
「食べてはいけない」と言われる理由は、観賞用アロエの摂取による健康被害リスクと、食用種でも皮や黄色い樹液に含まれる刺激性成分にあります。
葉の表面近くには、アロインやアントラキノンといった成分が含まれており、便秘改善に効果がある反面、過剰摂取すると腹痛や下痢などの副作用を引き起こします。
また、長期摂取で大腸メラノーシスのリスクもあります。
一方で適切に調理された食用アロエには、便秘改善、免疫機能向上、抗炎症作用、肌の保湿・鎮静効果などの健康効果が期待できます。アロエベラは比較的マイルドで料理に取り入れやすく、キダチアロエはより強い薬効が特徴です。
安全に摂取するには、必ず食用種を選び、皮と樹液を除去し、適量を守ることが重要です。妊婦や授乳中の方、小児、高齢者は特に注意が必要です。