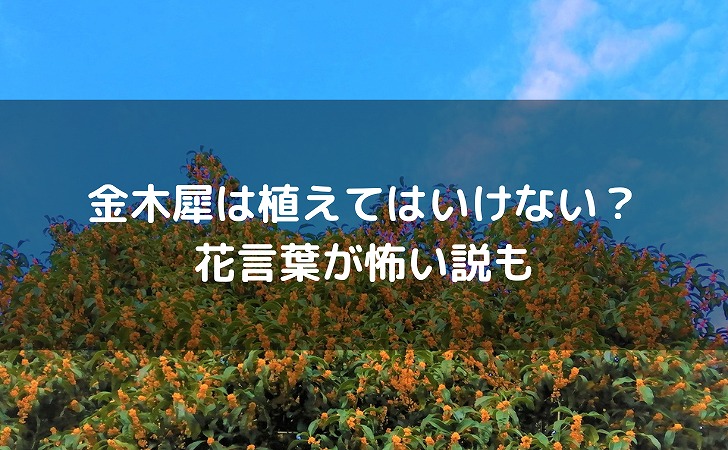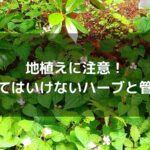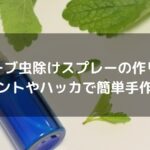金木犀は秋の花として日本では古くから愛されてきた樹木ですが、「金木犀は植えてはいけない」と言われる理由には何があるのでしょうか。
単純に、落ち葉や根が広がることでご近所迷惑になる以外にも、花言葉が怖いという理由が挙げられることが多いので、実際のところはどうなのか調査してみました。
結論としては、金木犀を植えることで起こるデメリットは確かにあるものの、必ずしも植えてはいけないと断定できるものではありませんでした。
金木犀を植えることで起こりうるリスクについて気になる方はぜひ参考にしてみてくださいね。
金木犀(キンモクセイ)とは?

金木犀(キンモクセイ)とは、モクセイ科モクセイ属の常緑小高木でモクセイの変種の一つです。
秋に橙黄色の花を咲かせて甘い香りを放ちます。その香りは沈丁花やクチナシとともに日本の三大芳香木と呼ばれています。
金木犀の花は小さくて可愛らしく橙黄色をしており、庭木や生垣として人気があります。
そんな金木犀ですが、時には「金木犀は植えてはいけない」と言われることがあり、その理由について次に詳しくお伝えしていきます。
「金木犀は植えてはいけない」と言われる4つの理由

大木となった金木犀
金木犀は人気のある植物ではありますが、「金木犀は植えてはいけない」と言われる理由として、主に以下の3つの理由が挙げられます。
- 生育旺盛で大きくなりすぎ、近所迷惑になる可能性があるため
- 花の強い香り・花粉症を引き起こす可能性があるため
- 花言葉が怖いと感じる人もいるため
- 害虫がつきやすいため
それぞれの理由についてもう少し詳しくお伝えしていきます。
金木犀を植える前にこうしたデメリットになる可能性について検討しておくと、後悔することは避けられるでしょう。
生育旺盛で大きくなりすぎ、近所迷惑になる可能性があるため
金木犀は、通常であれば4〜6mほどで成長する樹木ですが、条件が良いと10m以上になることもあります。
土や気候の条件などが揃えば、さらに大きく育つこともあるようです。
大木になってしまうので、剪定をしないと枝葉が周囲に広がってしまいます。これは、家の日当たりや風通しを悪くしたり、落ち葉や花びらが散らかったりすることで、自分や近隣の住民に不快感や手間をかけさせるなど迷惑をかけてしまう可能性があります。
特に金木犀の落葉問題によって近所迷惑やトラブルの原因になることは珍しい話ではありません。
また、根が強く庭の地中に深くまで広がるため、植え付け場所によっては周囲の植物の生育を妨げるだけでなく近所の敷地まで伸びていく恐れもあります。
金木犀の生育旺盛な性質を考えると、自宅の庭に植えるのをためらわれる人も少なくないでしょう。
花の強い香り・花粉症を引き起こす可能性があるため
金木犀は秋に強い香りを放つ花を咲かせますが、この香りが苦手(トイレの芳香剤に似ているなど)だと感じる人がいたり、気分を悪くする人もいます。
そのほか、花粉症やアレルギーを持つ人は、金木犀の香りに不快感や不安感を覚えることもあります。
金木犀の花粉は、スギやヒノキなどに比べて飛散量や飛散距離が少ないため、花粉症の原因としてはあまり知られていませんが、スギによる花粉症(目のかゆみや鼻水、くしゃみ、喉の違和感など)と似た症状を引き起こすことが多いとされています。
実際に、家の近所に金木犀を植えないようお願いしている人もいるようです。香りだけではなく花粉症が強くなるのが原因とのことです。
そのほか、金木犀の花粉によって喘息発作を発症させる可能性についても指摘されています。
毎年、キンモクセイが咲くと喘息発作で受診される方がおられます。
引用:医療法人 和平会HP
花言葉が怖いと感じる人もいるため
金木犀の花言葉のひとつに「隠世(かくせい)」があります。
この「隠世」という言葉は「隠された世界」や「別の世界」という意味から、「死」や「あの世」を連想させるという解釈をする人もいるため、縁起が悪いと感じる方がいます。
ただし、この「隠世」という花言葉は一般的な花言葉辞典に掲載されていない「裏花言葉」とも言われる非公式なものなので、あまり気にし過ぎない方が良いとされています。
害虫がつきやすいため
金木犀の強い甘い香りは人間だけでなく、さまざまな虫たちをも引き寄せます。特に開花期(9月〜10月)には、この魅惑的な香りに誘われて多くの昆虫が集まってきます。
これは自然の中では素晴らしい生態系の一部ですが、住宅地で金木犀を植える際には考慮すべき重要な問題点となります。
アブやハチ類、チョウやガ、カメムシ、蟻類が金木犀に集まりやすいとされています。
金木犀を植える際の注意点
植えてはいけないと言われることがある金木犀ですが、適切な管理によって、金木犀の美しさと香りを楽しみながら、デメリットを最小限に抑えることが可能です。
植える場所の注意点
金木犀を植える場所の注意点については次のとおりです。
【十分なスペースの確保】
金木犀は成熟すると高さ6〜8mに達するため、上部や周囲に十分な空間が必要です。建物や電線から最低でも3m以上離しましょう。
【日当たりと風通し】
日当たりの良い場所を選びましょう。半日陰でも育ちますが、花付きが悪くなります。風通しの良い場所だと病害虫の発生も抑えられます。
【近隣への配慮】
強い香りが広がるため、隣家の窓や洗濯物を干す場所から離して植えることで、トラブルを避けられます。
【根の伸長を考慮】
金木犀の根は意外と広範囲に伸びるため、建物の基礎や地下配管から少なくとも2m以上離して植えるのが理想的です。
【土壌条件】
水はけの良い肥沃な土壌を好みます。粘土質の場所では、植え穴に腐葉土や堆肥を混ぜ込むことで環境改善を図りましょう。
適切な剪定方法と時期
金木犀を育てるのに欠かせない剪定のポイントは次のとおりです。
【最適な剪定時期】
花後の11月から2月の休眠期が最適です。この時期なら翌年の花付きへの影響を最小限に抑えられます。
【基本的な剪定方法】
- 混みあった内側の枝を優先的に間引く
- 枯れ枝や病気の枝を取り除く
- 樹形を整えるために伸びすぎた枝を切り詰める
- 全体の3分の1程度を目安に剪定する
【避けるべき剪定時期】
6月中旬以降の剪定は翌年の花芽を切り落とすことになるので避けましょう。
【若木の剪定】
植えたての若い木は最低2年間は剪定を控え、根が十分に張るのを待ちましょう。
根の成長をコントロールする方法
根が広がるのを防ぐために、成長をコントロールするのも手段の一つです。
【植え付け時の工夫】
初めから根の広がりをコントロールしたい場合は、植え穴の周囲にルートバリア(根の侵入を防ぐシート)を設置します。
【定期的な根切り】
2〜3年に一度、樹冠の外周部分を円形に掘り起こし、太くなった根を適度に切り詰めることで、根の暴走を防げます。
【鉢植え選択肢】
完全に根の広がりを制限したい場合は、大型の鉢や植木鉢に植えることも検討しましょう。
【ルートコントロールバッグ】
地植えでも根を制限できる専用の不織布バッグを使用する方法もあります。
落花・落葉対策
排水溝の詰まりや近所迷惑にもなりかねない落花・落葉対策のポイントをまとめました。
【予防的対策】
- 植える前から落花・落葉が問題になりそうな場所(排水溝や池の近く)は避ける
- 下に砂利やウッドチップなどを敷いておくと掃除が楽になる
【収集方法】
- 開花期前に樹の下にネットを張っておくと、落花の回収が簡単になる
- 落葉期には定期的な清掃スケジュールを組んで対応する
【排水溝の保護】
特に雨どいや排水口の近くに植えている場合は、落花・落葉期に保護カバーを設置すると詰まりを防げます。
金木犀を鉢植えで小さく育てる方法
金木犀は鉢植えにすると1〜2m程度に育てることができます。鉢植えの金木犀を小さく育てるには、以下の方法が効果的です。
こまめに剪定をする
金木犀は、剪定をすることで枝が分岐し、茂っていきます。そのため、小さく育てたい場合は、こまめに剪定をして枝の伸びを抑えましょう。
剪定は、10月下旬〜12月上旬(花後)、または3〜4月下旬頃が適期です。真夏や真冬に剪定すると、生育に影響が出てしまうことがあるので注意しましょう。
剪定の方法は、以下のとおりです。
- 不要な枝を根元から切り落とす。
- 必要な枝は、葉を数枚残せるよう、横枝のすぐ上で切り戻す。
- 全体のバランスを見ながら、自然な樹形になるように剪定する。
鉢の大きさを調整する
鉢の大きさが小さすぎると、根詰まりを起こして生育が悪くなります。
根が鉢いっぱいになったら、同じ大きさの鉢に根を適度に剪定して植え替えるか、必要に応じて一回り大きな鉢に植え替えます。
植え替えは、3〜4月頃が適期です。鉢底石を敷いてから新しい鉢に植え替え、根をほぐしながら土を詰めましょう。
肥料を控えめにする
肥料を与えすぎると、枝が徒長して大きくなってしまいます。そのため、肥料は、春(3〜4月)と秋(9〜10月)に、薄めた緩効性の固形肥料や希釈した液体肥料を与えるだけで十分です。
日当たりをよくする
金木犀は、日当たりを好む植物です。鉢植えの場合は、日当たりの良い場所に置きましょう。
これらの方法を組み合わせることで、鉢植えの金木犀を小さく育てることができます。ぜひ試してみてください。
金木犀を植えるべきか検討する際のQ&A
ここでは、金木犀を植えるべきか検討する際のQ&A(質問&回答)を紹介します。
- 魔除けになるって本当?
- 風水的には縁起が良い?悪い?
- 植える方角はどこが良いか?
上記の問いについて詳しく回答していますので、参考にしてみてくださいね。
魔除けになるって本当?
金木犀は魔除けになると言われています。金木犀は強い香りが邪気や悪い運気を払うとされ、日本では古くから優れた魔除け効果を持つと伝えられてきました。
ただし、当然ながら科学的には証明されているものではないので、その点はご留意ください。
風水的には縁起が良い?悪い?
一般的に、金木犀は風水的には縁起が良いとされています。金木犀の金色の花は太陽を象徴し闇を払うという縁起物として捉えられています。
しかし、一方で金木犀は「縁起が悪い」と言われることもあります。これは、金木犀の花言葉のひとつに「隠世(かくせい)」があり、「隠された世界」や「別の世界」という意味から、「死」や「あの世」を連想させるという解釈をする人もいるためです。
この「隠世」という花言葉は一般的な花言葉辞典に掲載されていない「裏花言葉」とも言われ、非公式なものなので、あまり気にし過ぎない方が良いでしょう。
植える方角はどこが良いか?
金木犀は風水的に縁起の良い木とされていますが、植える方角は、東、東南、南西が良いと言われています。
特に、南西に植えると、邪気が祓われて金運が上がるという言い伝えがあります。
この方角は、午後から夕方になるまで日がたっぷり当たるので、風水的にはエネルギーの停滞しやすい場所とされており、香りの強い金木犀が浄化の役割を果たすとされています。
金木犀はオレンジ色の花を咲かせ、風水的には運気を高めるとされています。また、その香りにはアロマテラピー的にリラックス効果があるという意見もあります。
実用的な観点からは、金木犀を植えるときは日当たりの良い場所に植えることが大切です。日当たりが悪いと花が咲かなくなってしまうためです。
まとめ:金木犀は植えてはいけない4つの理由と小さく育てる方法
金木犀は秋の香りを代表する人気の樹木ですが、「植えてはいけない」と言われる理由には主に4つあります。
- 生育旺盛で大きくなりすぎ近隣トラブルの原因になる
- 強い香りや花粉症を引き起こす可能性がある
- 「隠世」という裏花言葉が怖いと感じる人がいる
- 害虫が集まりやすい
といった点です。
しかし、金木犀のデメリットは適切な管理で最小限に抑えることができます。植える際は十分なスペースの確保、日当たりと風通しの良さ、近隣への配慮、根の伸長を考慮した場所選びが重要です。
剪定は花後の11月〜2月、または3〜4月下旬が適期で、鉢植えで育てれば1〜2m程度のサイズに抑えることも可能です。小さく育てるコツは、こまめな剪定、適切な鉢の管理、控えめな肥料、十分な日当たりを確保することです。
また、金木犀は風水的に縁起が良いとされ、特に東、東南、南西方角に植えると良いという言い伝えもあります。
金木犀を植える際はこれらのメリット・デメリットをしっかり理解し、適切な管理をすることで、その美しさと香りを楽しむことができるでしょう。